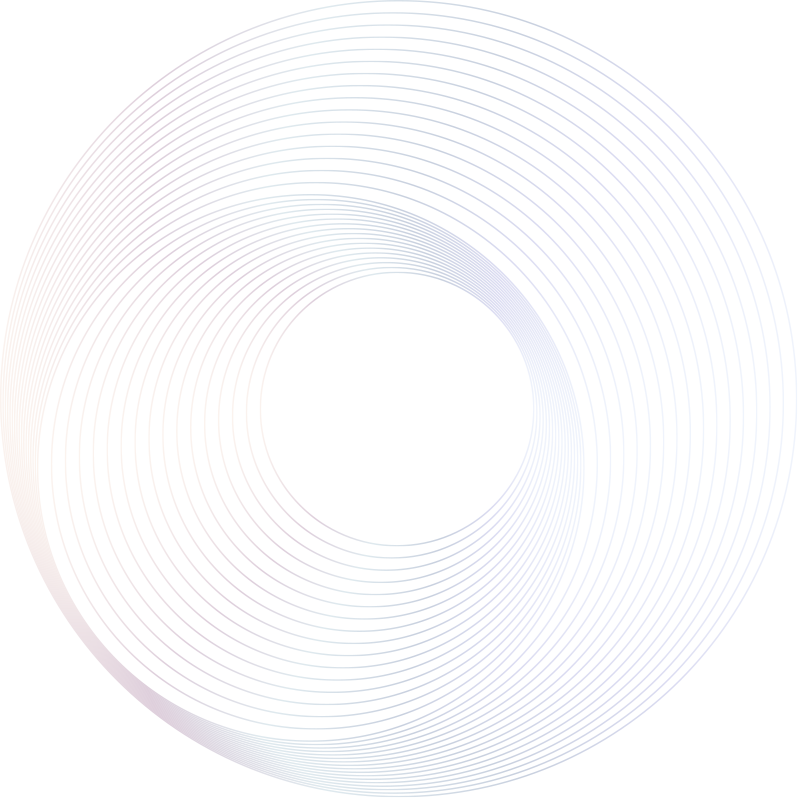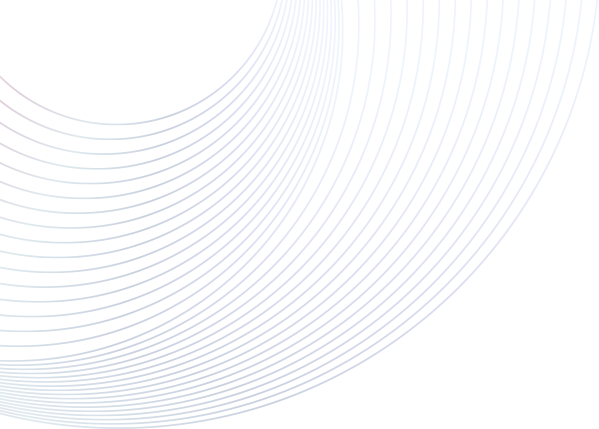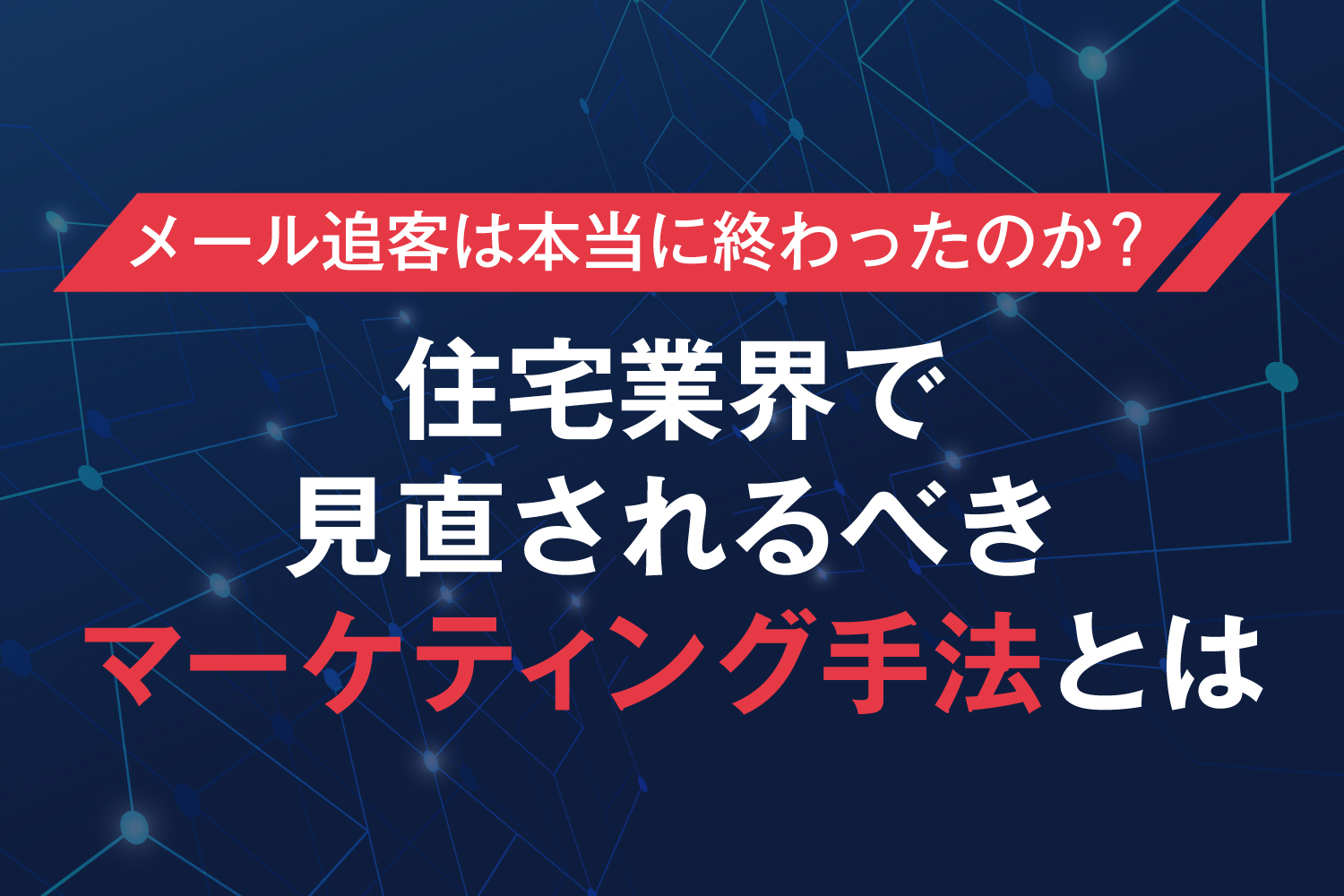
「メール追客はもう古い」と断言する人がいます。
しかし、本当にそうなのでしょうか?
たしかにメールを日常の連絡手段に用いる人が減っていることは事実です。しかし、住宅業界における追客手法として、メールはまだ十分に有効です。
この記事では、LINEが個人連絡ツールとして台頭する中で、メールという手法が引き続き持つ可能性と、最適な活用方法、またLINEとの併用という視点について解説します。
「メールはもう誰も読まない。LINEが主流だ」という声を耳にすることがあります。確かに、日常的なやり取りではLINEが中心になっていることは事実です。しかし、それをもって「メールは終わった」と結論づけるのは、やや早計といえるでしょう。
たとえば、LINEを主に使うユーザーが多い一方で、メールを日常的に確認するユーザーは少なくありません。
また、LINEは日本や韓国といった一部地域に特化したチャネルでありるという事実も忘れてはなりません。グローバルに見れば今なお多くの企業やサービスがメールを活用して情報提供を行っているのが現状ですから、メールは世界中の多くのインフラやサービスと連携しており、業界や国を問わず広く使われているという点でも、今後も一定の役割を担い続けると考えられます。
さらに、LINEとメールを用途によって使い分ける人も多く、たとえばLINEは親しい人との即時的な連絡、メールは情報の保存や確認に使うというスタイルも一般的です。
このように、複数の視点を踏まえれば、「LINEが主流=メールが不要」とするのは、やや単純化しすぎた見方と言えることがわかります。
インターネット上の各種調査や事例を見れば、現在でも多くの人が日常的にメールを確認しており、LINEと同等以上のリーチ力やコンバージョン力を示すデータも少なくありません。つまり、メールはまだまだ重要なチャネルとして活用できる余地があるといえるでしょう。
追客の手段を一つに絞ることは、非常にリスキーです。特定のチャネルを過信するのではなく、さまざまな手段を面で捉え、複数チャネルを活用するのが現実的なアプローチといえるでしょう。
LINEは即時性があり便利なツールですが、通知が頻繁に届くことにストレスを感じる方も少なくなく、また匿名性が高いことから、営業的な追客でLINEを使用すると気軽にブロックされてしまうというリスクが高まります。
その点、メールは「自分のタイミングで読める」媒体です。プッシュ型のLINEとは異なり、プル型のメールは相手にストレスを与えにくいという利点があります。情報の受け取り手に主導権を委ねる手法として、今なお支持されているのがメールなのです。
以下に、LINEとメールのそれぞれの特徴・強み・弱みをまとめます:
・即時性が高く、反応スピードが速い
・通知がONのユーザーが多く、開封率が高くなりやすい
・個人的・カジュアルな印象を与えるため、親しみやすい
・その一方で、通知頻度が高くなると「ノイズ」と捉えられる可能性がある
・匿名性が高いため、ブロックが容易で、継続的な接触が困難になることがある
・業務連絡とは相性が悪く、プライベートな印象が強い
・プル型なので、受信者が自分のタイミングで確認できる
・情報を蓄積・保存しやすく、検索性も高い
・落ち着いて内容を確認してもらいやすいため、比較的丁寧な訴求が可能
・通知をOFFにしている人が多く、即時反応は期待しづらい
・ブロックされるリスクは低いが、迷惑メールフォルダに入る懸念はある
・開封率の平均は約30%、クリック率は約5%と数字としては安定しており、CV率が高い傾向にある
このように、両者にはそれぞれ異なる強みと弱みがあります。
また、特にZ世代ではLINEを「個人的なやり取り専用のツール」と認識する傾向があり、企業との関わりに用いることに抵抗感を覚えるユーザーも少なくありません。このような感覚は、追客チャネルとしてLINEを選ぶ際に留意すべき要素といえるでしょう。
どちらか一方に依存するのではなく、目的やターゲットに応じて適切に使い分けることが重要です。
マーケティングの最適解は、エリアやターゲット層によって異なります。たとえば、郊外や地方の住宅検討者層に対しては、Web広告やメールよりもチラシや電話の方が効果的とされるケースもあります。特にリアルでの接点や紙媒体に慣れている層に対しては、アナログな手法がむしろ刺さるという状況も考えられます。
同様に、メールが刺さるターゲットも存在します。「この手法はもう古い」と決めつけるのではなく、自社の顧客層にとって何が最適かを見極める視点が求められます。
一部の業者が「メールはもう古い。やめたほうがいい」と主張する背景には、自社サービスへの誘導という意図がある場合もあります。参考にすべき内容を含む場合もありますが、つまり、それはポジショントークとしての側面を持っているケースもあるということですので留意する必要があります。
現場のマーケティング担当者に求められるのは、その言葉を鵜呑みにするのではなく、自社のデータと顧客理解に基づいてチャネルを選ぶ冷静な判断力です。
メールは確かに万能ではありません。また、日常のやり取りにメールを用いる方が減っていることは間違いないでしょう。しかし、「もう使えない」と切り捨てるのは早計です。ターゲットによっては、メールが最も自然に届くチャネルとなることもあります。
最も重要なのは、媒体ごとの良し悪しを単純に比較するのではなく、それぞれの特性を理解し、適切に組み合わせて活用する戦略的な視点です。LINE、SMS、チラシ、電話、そしてメール。それぞれに役割があります。
住宅業界の追客においては、「これだけやればいい」という単純な答えは存在しません。複数チャネルを活用した“面”でのアプローチこそが、これからの時代に求められる追客の姿勢といえるでしょう。