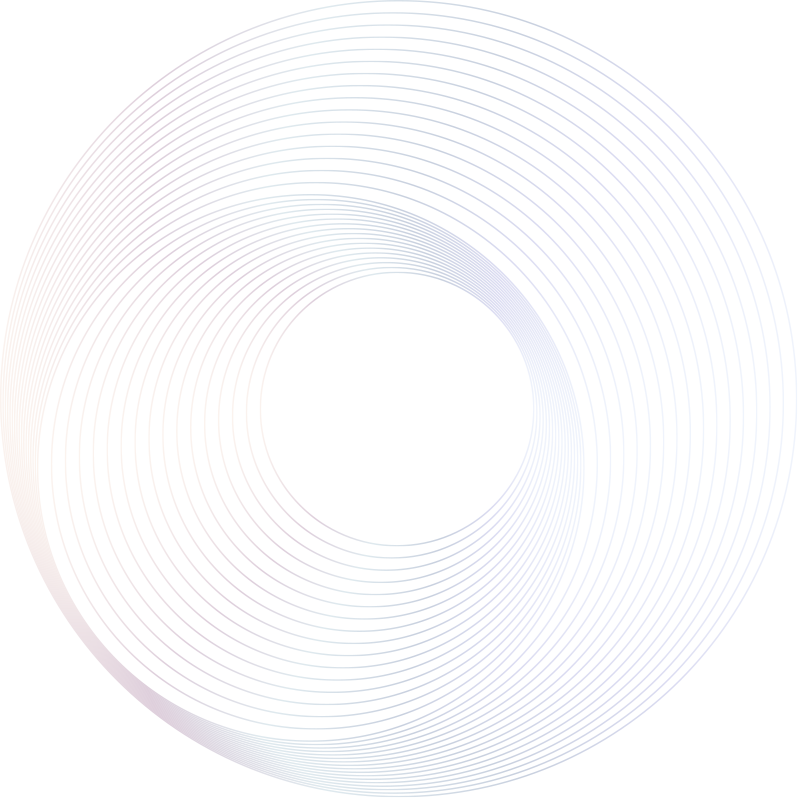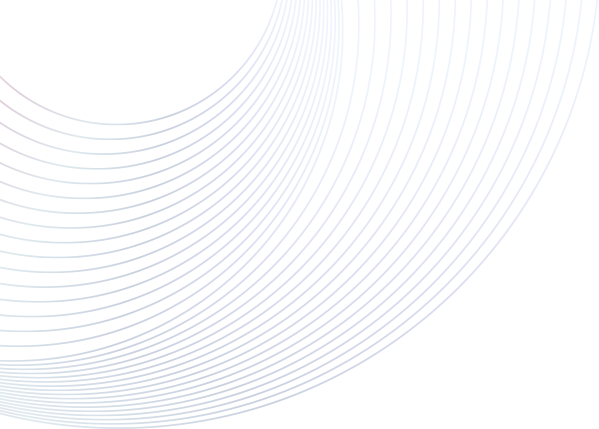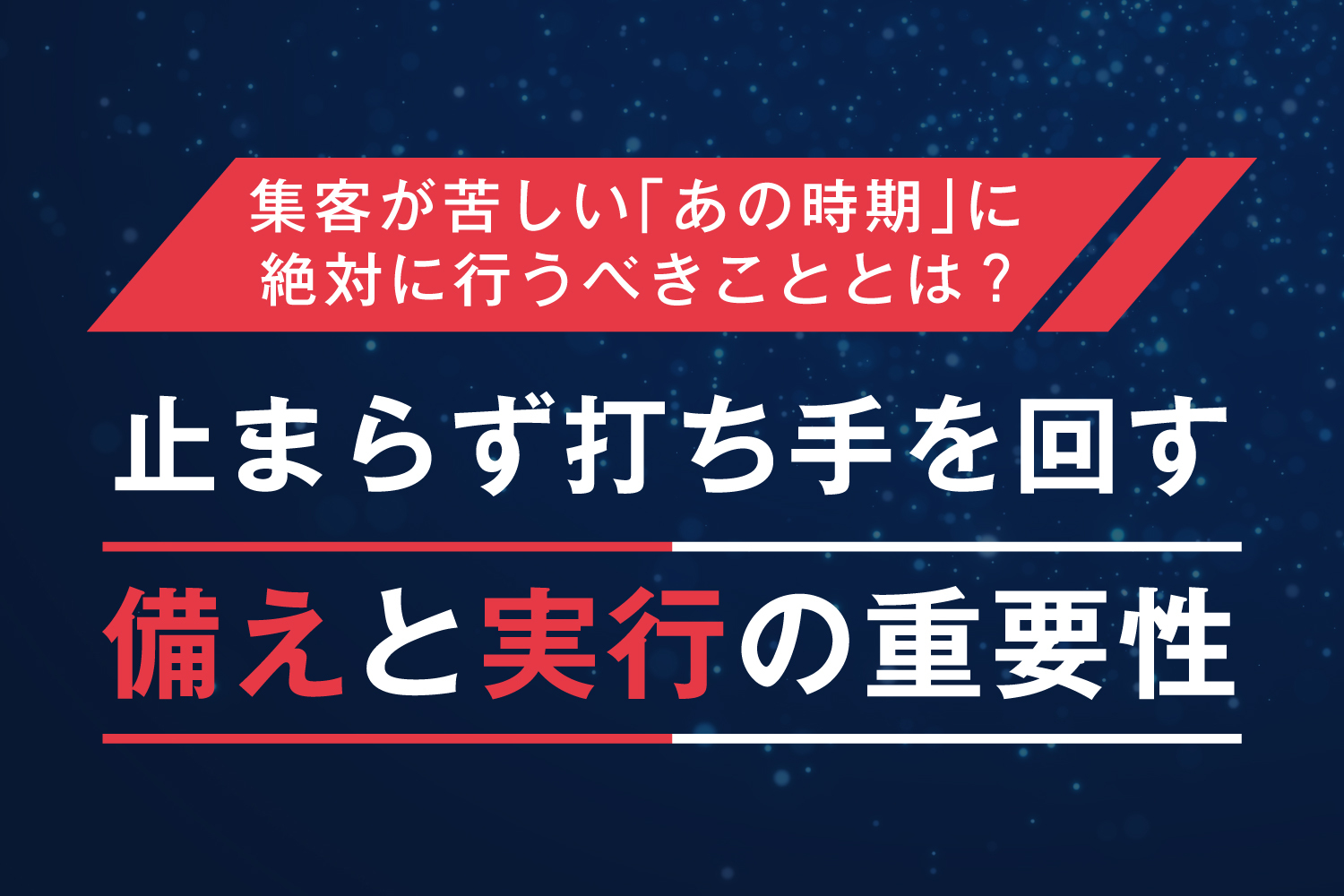
「毎年〇月は集客が苦しい…」
「年末年始や夏など、集客が極端に落ち込む時期に、何をすればいいのかわからない!」
これは、ほぼすべての住宅会社に共通する悩みと言っても良いでしょう。
特に地方の工務店などでは、気候や時期によって来場数が大きく変動し、思うように動けない時期が出てくるものです。
しかし、そうした“動きづらい期間”こそ、やるべきことは確実にあります。
この記事では、集客が落ち込む時期に住宅会社がとるべき行動と、事前に準備しておくべき備えについて解説します。
読めば「いざという時に慌てないための引き出し」が手に入り、どんな状況でも一歩前に踏み出せる自信が持てるはずです。
住宅会社の集客は、どうしても広告やイベントといった単発の“打ち出し施策”に偏りがちです。
そのため、たとえば広告を打って成果が落ちると「反応が鈍くなった」と判断し、止めてしまうケースもあります。
しかし、こうした状況では単一の打ち手に依存せず、“面”での施策を再点検することが求められます。
広告に加え、DM・チラシ・ポスティング・電話フォロー・OB施策など、取り得るあらゆる手段を洗い出し、今できることを予算や人手に応じて組み合わせていきましょう。
この「地に足のついた整理と実行」が、実は最も効果的なアプローチなのです。
集客が苦しい時期ほど、「今すぐ客」ばかりを探しにいくのではなく、「既に接点のある見込み客」へ目を向けることが重要です。
たとえば、過去に資料請求をくれた方、来場はしたけれど商談化に至らなかった方、さらにはOB客など、どんな会社でも必ず複数のリストがあるはずです。
こうしたリストに対し、電話やLINE、手紙などでコンタクトを取り、少しでも動線を生み出すことができます。
その前提として、見込み顧客リストが全社で一元的に管理されていることが欠かせません。情報が各担当者に分散していたり、最新状態が共有されていなかったりすると、有効なアプローチができず、機会を逃してしまいます。
そのためにも、マーケティングオートメーション(MA)ツールなどを活用して、見込み顧客の属性・ステータス・接触履歴などを可視化しておく仕組みが必要です。
派手な施策でなくても、丁寧に取り組めば2〜3件の来場につながる可能性があり、そこから商談へと展開していく流れをつくることができます。
年末年始や猛暑の夏など、来場が減るタイミングは、毎年ある程度予測ができます。
もちろん、年によって状況は変わるため完全な読みは難しいものの、「この時期は落ち込みやすい」という傾向は過去のデータからも見えてくるはずです。
だからこそ、そうした“下がる時期”を前提に、あらかじめプランBを用意しておくことが肝要です。
広告が鈍化したらDMを巻く、来場が止まったら電話を入れる、反応が鈍いと感じたら紹介キャンペーンを仕掛ける──こうした“次の一手”が準備されていれば、いざという時に迷いなく実行できます。
重要なのは、「集客は自分たちの責任だ」という意識を全社で持つことです。
集客が落ち込んだときに「広告が悪い」とか「この季節は仕方ない」と外部要因に逃げてしまうと、動くべきタイミングを逃してしまいます。
社長だけでなく、現場のスタッフ一人ひとりが、「来場が少ない=自分たちが動くタイミング」と認識し、目標数と実績の差分を早期にキャッチして対策を講じる──
この思考と行動の連動が、打開策を生む鍵になります。
どの会社にも、集客がうまくいかない時期はあります。
差が生まれるのは、そのときに止まってしまうか、それでも手を打てるか、という姿勢の違いからです。
すべての打ち手を一気に行う必要はありません。しかし、電話をかける、DMを送る、紹介を呼びかけるなど、小さくとも“やれること”を確実にやっていく会社は、やがてチャンスを引き寄せます。
「苦しいときにこそ、動ける力を持つ」ことの重要性を再認識し、いざというときの行動に迷わない準備を整えておきましょう。