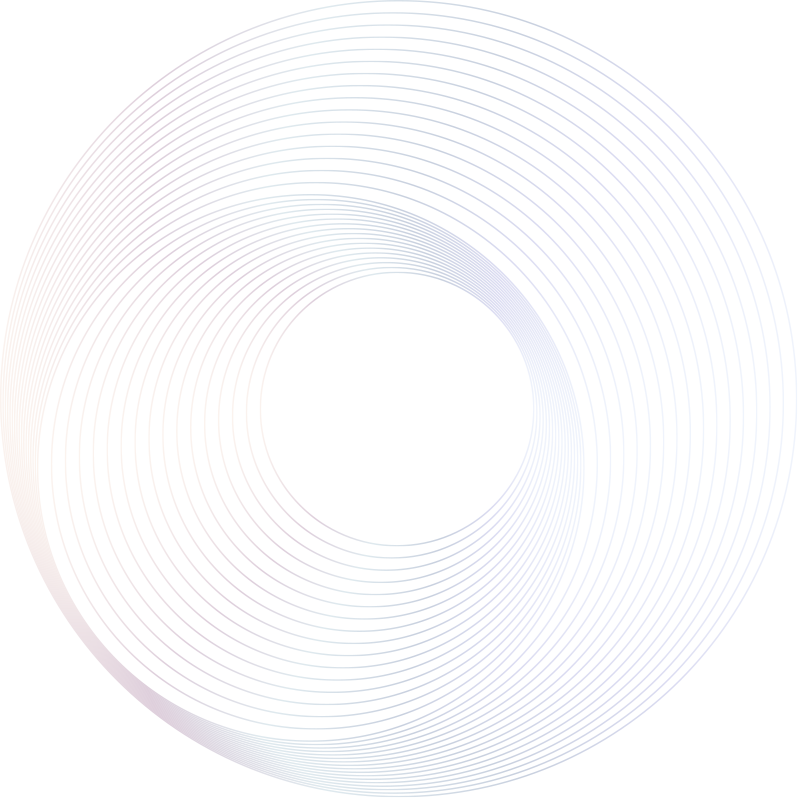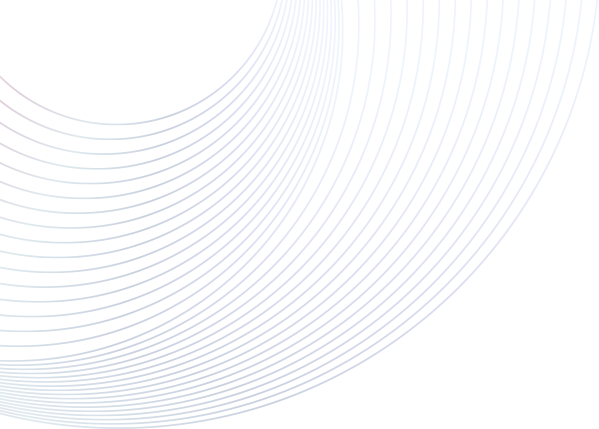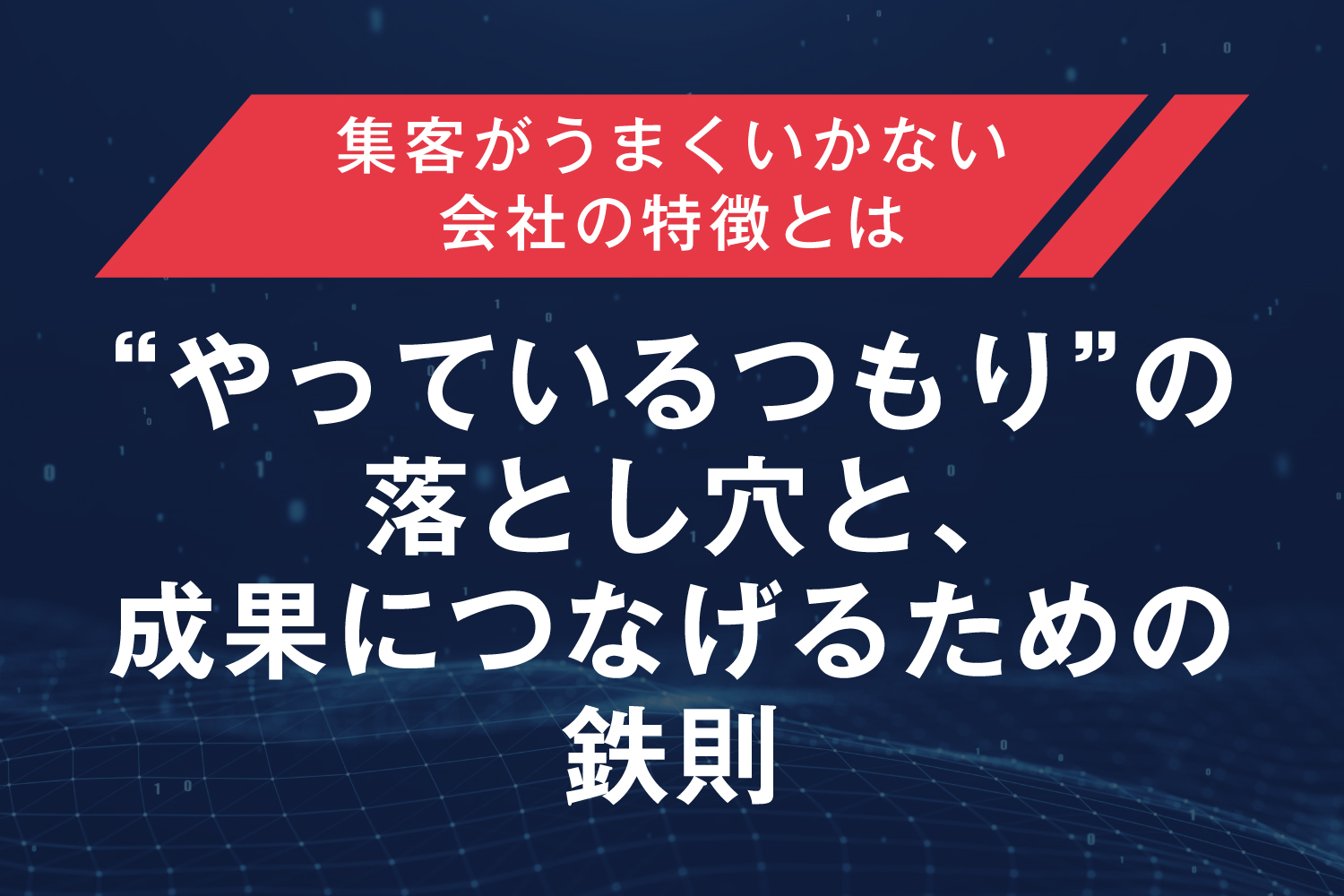
「いろいろな施策を試しているのに、どうしても集客につながらない」
「競合のA社はうまくいったのに、うちで同じ施策をやっても集客できない」
住宅会社のマーケ担当者さんや経営者さんからよく聞こえてくる悩みです。
特に最近では、SNS広告やLP改善、マーケティングオートメーションなど、さまざまな手法が注目されている中で、手を尽くしているはずなのに成果が見えない、というケースが後を絶ちません。
この記事では、そうした“努力しているのに結果が出ない”会社に共通する特徴と、実際に成果を出すために押さえておきたいポイントについて整理していきます。
読めば「どこでつまずいているのか」や「何を改善すべきか」がはっきりし、集客の打ち手に自信を持って取り組める状態になれるはずです。
さまざまな施策に取り組んでいるように見えて、実はどれも中途半端に終わっている。
これが、集客がうまくいかない住宅会社の最も大きな特徴です。
たとえば、広告を出してはいるが「とりあえず配信してみた」で止まっている。イベントページを作っても、ABテストや改善を繰り返す運用体制がない。あるいは、問い合わせがあっても追客の仕組みが整っておらず、見込み客を取りこぼしてしまう。
──こうした“60点にも届かない取り組み”が成果を妨げています。
大前提として、広告でもSNSでも、基本的にはどこかの会社が既に成果を出している手法です。
つまり、やり方が間違っていなければ、一定の成果は出る可能性が高いといえます。
問題は、その方法を「どこまでやり切れるか」、ということなのです。
途中で「思ったより反応がない」と感じて手を止めてしまえば、当然結果は出ません。
期待が高すぎたり、検証を待たずに諦めてしまったりといった“早すぎる判断”こそが、成果を遠ざける要因になっているのです。
それから、形ばかり表面的にマネをして、本質を理解したり、自社の現状に合わせて調整を繰り返したりすることも怠ってはいけません。
これが「やりきる」ということであり、ほとんどの会社ができていないことです。
では、どうすればやり切れるのか?
ポイントは「継続的にPDCAを回す仕組みをつくること」にあります。
たとえば、広告であれば2〜3日に一度、キャッチコピーやバナーの検証結果をチェックし、改善案を出して実行する。
そのサイクルを会社の定例ミーティングに組み込んだり、外部パートナーと週1回の改善ミーティングを設けたりすることで、“やらざるを得ない”環境をつくることが重要です。
また、単にやるだけでなく、「その結果をどう読み解くか」「次に何を試すか」といった思考の積み重ねが、成果への近道になります。
「まずは3ヶ月回してみましょう」──よく聞くアドバイスですが、新しい施策や広告などにおいてはこれは危険な考え方です。
たとえば、実際には広告の効果は数日で見えてくるケースも多く、初動の反応をもとに速やかに改善していくことが鉄則です。
“反応がないのに3ヶ月放置する”というのは、もはや検証ではなく“思考停止”でしかありません。
だからこそ、細かくPDCAを回し、思考と行動の回数を積み重ねることで、ようやく反応が形になって見えてくるのです。
新しい手法に取り組むこと自体は、何も間違いではありません。しかし、その多くは“着手しただけ”で止まっており、成果が出るまでに必要な思考・改善・継続といったプロセスが抜け落ちています。
本気で集客を改善したいなら、必要なのは“泥臭く数字と向き合い続ける姿勢”です。
そのための仕組みをつくり、考える時間を確保し、社内やパートナーと連携しながら、成果が出るまで粘り強くやり続ける──それが、結果につながる唯一の道筋です。
「どんな手法を使うか」よりも、「どこまでやり切れるか」。ぜひ、自社の取り組みを今一度見直してみてください。